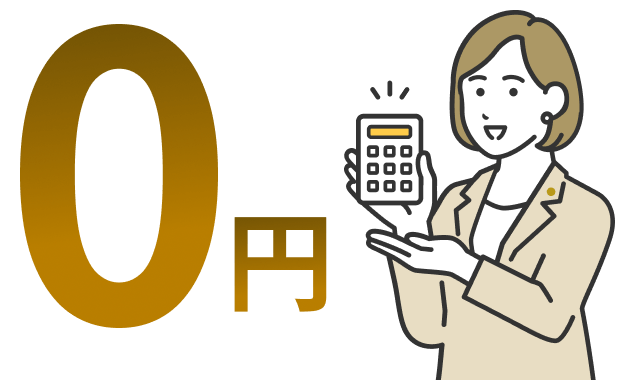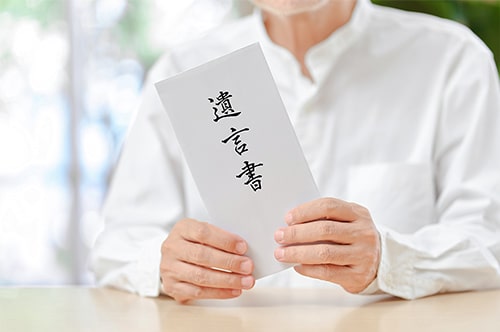疎遠な相続人がいるときの遺産相続の進め方や手紙の書き方
- 遺産を受け取る方
- 疎遠な相続人
- 手紙

相続手続が行われず、所有者が分からなくなった土地を「所有者不明土地」といいます。
こうした土地が年々増える原因のひとつに、「遺産分割」が行われず放置されることが挙げられます。遺産分割は、相続人全員の合意が必要です。疎遠な相続人と連絡を取ることに負担を感じる方は少なくないでしょう。
本コラムでは、疎遠な関係にある相続人に対して手紙を送る際のポイントや文例、応答がない場合の対処法などについて、ベリーベスト法律事務所 大分オフィスの弁護士が解説します。


1、疎遠な相続人がいるときの遺産相続の進め方
相続手続の大まかな流れや疎遠な相続人がいる場合の注意点を解説します。
-
(1)相続手続の流れ
相続手続の大まかな流れは以下のとおりです。
それぞれ詳しくみていきましょう。
① 相続人の調査
亡くなった方(被相続人)の出生から死亡までの戸籍、相続人の現在までの戸籍を取り寄せて相続人を調査します。この段階で、被相続人が過去にもうけた子など、交流のない疎遠な関係の相続人が判明することもあるでしょう。
② 相続財産・債務の調査
相続の対象となる被相続人の財産や債務の種類、評価額を調査していきます。
③ 相続放棄・限定承認
債務が多いなどの理由で相続したくない場合は、原則として、相続の開始があったことを知った日から3か月以内に家庭裁判所で相続放棄の申述を行う必要があります。
相続放棄をすると「相続人ではなかった」ことになるため、相続手続に参加する必要はありません。また、財産と債務(借金など)のどちらが多いかはっきりしない場合には、遺産で債務を清算して残った財産があれば相続する「限定承認」も選択肢となります。
限定承認については、相続人全員で家庭裁判所に申し立てをしなければなりません。
④ 遺産分割協議
相続人全員で協議を行い、誰がどの遺産を取得するのか全員の合意で決定します。
協議がまとまれば、合意の内容をまとめた遺産分割協議書を作成することになります。遺産分割を行うべき明確な期限はありませんが、相続税の申告期限である10か月以内を一応の目安として考えておくとよいでしょう。
⑤ 名義変更
遺産分割協議書をもとに、被相続人名義の預貯金の払い戻しや不動産などの名義変更手続を進めていきます。
⑥ 相続税の申告・納付
相続税が課税される場合は、遺産分割ができているか否かに関わらず、相続の開始があったことを知った日の翌日から10か月以内に申告と納付を行わなければなりません。 -
(2)疎遠な相続人を無視するとどうなる?
相続人全員で行う必要がある手続は限定承認と遺産分割ですが、これらを一部の相続人のみで行っても、法的な効力は生じません。
たとえば、一部の相続人のみで遺産分割協議書を作成しても、相続人全員の署名や押印がなければ、預貯金の払い戻しや不動産の登記名義の変更には応じてもらえないのです。このため、疎遠であっても必ず全ての相続人と連絡を取り、協議に参加してもらう必要があります。 -
(3)疎遠な相続人の所在が不明の場合
疎遠な相続人の住所が分からない場合は、「戸籍の附票」という住民票上の住所が記載された書類を取り寄せて調べることが可能です。
しかし、戸籍の附票に記載された住所に実際に居住しておらず、連絡先も一切分からないケースも存在します。
そのような場合でも、その相続人を遺産分割から除外することはできないため、次のいずれかの手段により手続を進めていく必要があります。
① 不在者財産管理人の選任
行方不明となっている人(不在者)の代わりに本人の財産を管理する管理人の選任を家庭裁判所に申し立てて、選任された管理人に遺産分割に参加してもらうことができます。
管理人の人選は家庭裁判所が行いますが、相続に関係のない親族や弁護士などが選任されるのが一般的です。
② 失踪宣告の申し立て
音信不通となって長期間が経過している場合、家庭裁判所に「失踪宣告」の申し立てをする方法もあります。
失踪宣告とは、生死不明の状態にある不在者を法律上死亡したものとみなす制度です。
失踪宣告が認められるのは、以下のいずれかに該当するケースです。- 生死不明となって7年以上経過した場合(普通失踪)
- 災害や遭難、海難事故などの危難に遭って生死不明となり、危難が去ってから1年経過した場合(特別失踪)
なお、失踪宣告により死亡したものとみなされることになった場合は、不在者の相続人や代襲相続人(子や孫)が相続手続に加わることになります。
2、疎遠な相続人への手紙の書き方
疎遠な関係にある相続人へ最初に送る手紙の書き方について解説します。
-
(1)疎遠な相続人へ最初の手紙で伝える情報
疎遠な相続人の場合、人柄や生活状況など分からない部分も多いでしょう。
そのため、最初の手紙でどこまで情報を伝えるべきか、正解があるわけではありません。まずは相続手続のために連絡を取り合える関係を築くことを目的として、以下の内容を簡潔に伝えるのが順当といえるでしょう。疎遠な相続人に伝えるべき項目- 相続発生の事実・日時
- 共同相続人になったこと
- 遺産分割協議を行う必要があること
- 相続に関わりたくない場合でも返信してほしいこと
- 返信してほしい期限
- 今後の連絡方法についての希望
相続財産の内容や評価額などの重要な情報は、先方の意向を確認した上で共有していくのもひとつの方法です。
-
(2)手紙の一例
疎遠な相続人へ最初に送る手紙の文例をご紹介します。
拝啓 突然のお手紙で失礼いたします。
故 ○○○○は、令和○年○月○日に大分市内で永眠いたしました。 私は故人の長男で相続人となる者ですが、相続に関する手続を進める中で、○○様も相続人であることが判明いたしましたので、お手紙を差し上げた次第です。
相続財産の分配については、法律上、相続人全員による遺産分割協議が必要となります。つきましては、○○様にも遺産分割協議にご参加いただきたく存じます。
なお、相続手続に関わりたくないというご意向がある場合でも、その旨をお知らせいただくようお願いいたします。
ご返信は、令和○年○月○日までにいただけますようお願いいたします。今後のご連絡は、お電話、郵便、またはメールのいずれかの方法で承りたいと存じます。ご都合の良い連絡方法をお知らせください。
敬具
(連絡先)
〒✕✕✕-✕✕✕✕ ○○市○町✕―✕
○○一郎
電話:✕✕✕-✕✕✕-✕✕✕✕
メール:✕✕✕✕✕@✕✕✕✕✕.✕✕
上記はあくまで一例です。相続の相談窓口を設けている自治体もあるため、迷った場合は、問い合わせてみることをおすすめします。
お問い合わせください。
3、疎遠な相続人から手紙の返事が来なかった際の対処法
疎遠な相続人に手紙を送っても応答がないケースもあります。
応答がない理由としては、返答に迷っている場合や面倒なことに関わりたくないという意向、あるいは多忙や病気療養中などの事情が考えられるでしょう。
しかしながら、相続手続を進めるためには、このような状況でも次の手段を講じることが必要です。
-
(1)再度手紙を送る
先方の事情が分からない状況では、再度返信期限を設けて手紙を送るのが穏便な方法といえるでしょう。2回目の手紙を送る際には、配達されたことが確認できる特定記録郵便やレターパックなどを利用することも考えられます。
-
(2)住所を訪問する
自宅を訪問して直接依頼することも選択肢となります。転居や長期の留守により手紙が読まれていない可能性もあり、実際に居住しているかの情報が得られるかもしれません。
なお、不在者財産管理人の選任や失踪宣告の申請をする場合には、最後に確認できる住所地で居住状況を確認する必要があります。 -
(3)弁護士などに相談する
相続手続で行き詰まってしまった場合は、弁護士などのサポートを受けることをおすすめします。
疎遠な相続人と連絡が取れない状況でも、遺産分割協議の準備や家庭裁判所へ調停を申し立てるタイミングについてアドバイスを受けることは有意義といえます。また、弁護士名義で通知書を出すことで、相手方に対応してもらえることも期待できます。 -
(4)遺産分割調停を申し立てる
話し合いにより遺産分割ができない場合は、家庭裁判所の調停や審判の手続により遺産分割を行うことになります。
調停とは、家庭裁判所で調停委員の仲介により話し合いを行う手続のことです。調停でも話し合いがまとまらない場合は、家庭裁判所の判断により遺産分割を行う審判手続に移行します。
家庭裁判所で調停が成立したり審判で判断が示されたりした場合は、調停調書や審判書が遺産分割協議書の代わりとなり、相続手続を進めることが可能となります。
お問い合わせください。
4、疎遠な相続人を放置したまま遺産分割を行わないリスク
相続人と連絡が取れないと遺産分割は行えませんが、そのまま放置することにもリスクがあります。
遺産分割を行わないことによるリスクについて解説します。
-
(1)不動産を活用・処分できない
相続が発生すると、不動産は遺産分割を行うまで相続人全員が共有する状態となります。賃貸、売却、リフォーム等が原則としてできないうえ、固定資産税や管理費用は負担しなければならない状態が続きます。
また、不動産を相続した場合には、相続登記などの登記申請をすることが義務化されているので注意が必要です。
不動産を相続したことを知った日から3年以内に必要な登記申請をしないと10万円以下の過料に処せられることがあります。 -
(2)預貯金が払い戻せない
被相続人名義の預貯金は相続人全員の合意がなければ払い戻しを受けることができません。
なお、遺産分割前でも預貯金の一部について相続人が単独で払い戻しを受けられる制度もありますが、全額ではないので、預貯金の大半が凍結状態になってしまうおそれがあります。 -
(3)相続税の軽減が受けられない
相続税には配偶者控除や小規模宅地等の特例のように、大幅に税負担が軽くなる制度があります。
これらの軽減制度の適用を受けるためには、遺産分割を完了して申告期限までに申告することが必要です。3年以内に遺産分割を行って改めて申告することで、軽減が適用されることもありますが、いったんは高額な相続税の納付が必要になる場合があります。 -
(4)遺産を無断で処分される可能性
遺産分割を行わずに遺産を放置すると、無断で処分されたり所在が分からなくなったりするリスクも生じます。
また、相続発生から日時が経過してから相続財産の調査をしようとしても、資料が散逸したり記憶が薄れたりして難易度が高くなることもあるでしょう。 -
(5)数次相続により相続関係が複雑になる
遺産分割を行わないまま相続人が亡くなると、新たな相続(二次相続)も発生し、二次相続の相続人を加えて遺産分割を行う必要があります。
相続人の人数が増えたり、疎遠な関係の相続人が増えたりすることで、遺産分割が難航する可能性が高くなります。
5、まとめ
疎遠な関係であっても、法律上相続人となる方を無視して相続手続を進めることはできません。
手紙を送るなどの方法で連絡を取り、遺産分割に参加してもらうなど、手続への協力を求める必要があります。
また、疎遠な相続人がいる場合や話し合いがまとまらない場合でも、遺産分割を行わずに放置することには少なからぬリスクが伴います。相続手続について不明な点がある場合や将来的なトラブルを防ぎたいときは、専門家である弁護士のサポートを受けながら手続を進めることをおすすめします。
ベリーベスト法律事務所では、相続全般に関するご相談を随時承っております。疎遠な相続人と連絡が取れない、あるいは手続に協力してもらえないなどでお困りの際には、ベリーベスト法律事務所 大分オフィスにご相談ください。
- この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています