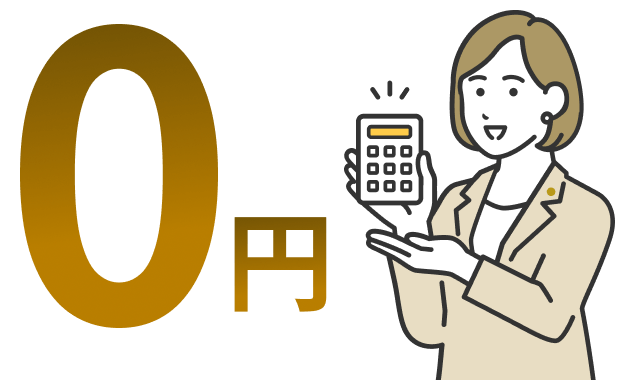共有持分の相続|不動産の共有名義人が亡くなった際の流れや注意点
- 遺産を受け取る方
- 共有持分
- 相続

不動産を家族で共有していると、誰かが亡くなったときに「共有持分」をどう相続するかで悩むことがあります。特に、名義人の一人が亡くなった場合、その持分をどう分け、誰がどのように相続登記をするのかを巡って、相続人間でトラブルになることも少なくありません。
この記事では、共有名義人の死亡時に発生する共有持分の相続の流れや、遺産分割協議の進め方、さらに実際に起こりがちなトラブルとその対処法について、ベリーベスト法律事務所 大分オフィスの弁護士が解説します。


1、共有名義の1人が亡くなった場合、共有持分の相続はどうなる?
家や土地などの不動産は、ひとりで持つだけでなく、家族やきょうだいと共有していることがあります。たとえば、登記事項証明書という書類を見て、「共有者」や「持分〇分の〇」と書いてあれば、その不動産は共有になっています。
では、その共有者のうちのひとりが亡くなったとき、残された共有者に自動的にその人の持分が移るのでしょうか?
答えは「いいえ」です。
亡くなった人の共有持分は、他の共有者にそのまま渡るわけではなく、相続財産のひとつとして扱われます。つまり、持分も相続手続きの対象になるのです。
このとき、誰が相続するかは法律で決まっています。共有者だからといって、残された人が優先的に持分を引き継げるわけではありません。たとえば、夫婦で共有していた場合でも、亡くなった夫の持分は自動的に妻のものにはなりません。相続人全体で話し合って決める必要があります。
- 基本的に配偶者と子ども
- 子どもがいないときは親や兄弟姉妹
原則として、共有持分は上記が相続人になります。亡くなった人が持っていた不動産の一部は、遺産として他の財産と同じように相続されるのです。
そのため、共有名義の不動産があるときは、持分の相続をめぐって話し合いが必要になったり、思わぬトラブルが起きたりすることもあります。生前から共有の内容を確認し、相続後の手続きについても知っておくことが大切です。
2、共有持分を相続する流れ
不動産を家族で共有していた人が亡くなると、その人が持っていた「持分」も相続の対象になります。この場合、ほかの相続財産と同じように、相続の手続きを進めていく必要があります。
ただし、どう進めるかは「遺言書があるかないか」によって変わってきます。以下では、一般的な手続きの流れを、順を追ってわかりやすく紹介します。
-
(1)遺言書の内容を確認する
まず初めに、亡くなった人が遺言書を残していたかを調べます。
遺言書がよく保管される場所
- 机の引き出し
- 金庫
- 銀行の貸金庫
- 公証役場
- 法務局
もし遺言書があれば、基本的にはその内容に沿って手続きを進めます。ただし、故人が自分で書いた遺言書(自筆証書遺言)は、そのままでは使えません。家庭裁判所に申し立てをして「検認」という確認作業を受ける必要があります。
一方、公証役場で作成された「公正証書遺言」や、法務局に預けた遺言は、検認の手続きは不要です。
このように、遺言の種類によって必要な手続きが異なる点に注意しましょう。 -
(2)相続人を確定させる
遺言書がない場合には、誰が相続人になるのかを確定する作業が必要です。
具体的には、亡くなった人の「生まれてから亡くなるまでの戸籍」を集めて、家族関係を確認します。戸籍をたどっていくことで、だれが法律上の相続人になるかがわかります。 -
(3)相続人全員で遺産分割協議を開始する
遺言書がなく、相続人が複数いる場合には、だれがどの財産を受け取るのかを決めるために話し合いをします。これを「遺産分割協議」といいます。
法律では、相続人は法定相続分に従って遺産を受け継ぐことになっています。しかし、みんなが合意すれば、自由に分け方を決めることも可能です。
たとえば、不動産は長男がもらい、次男は預金を多くもらうといった調整もできます。この話し合いは、不動産だけでなく、他の財産についてもまとめて行うのが一般的です。 -
(4)遺産分割協議書を作成する
遺産の分け方について相続人全員の話し合いがまとまったら、その内容を正式な書面にまとめます。これを「遺産分割協議書」といいます。この書類には、基本的に、相続人全員が実印を押印し、印鑑証明書を添付する必要があります。
遺産分割協議書は、不動産の相続登記や銀行の名義変更など、さまざまな手続きで必要になります。あとで困らないように、内容に間違いがないかしっかり確認し、大切に保管しておくことが重要です。 -
(5)相続登記を行う
遺産分割協議書の作成が完了したら、不動産の名義変更、つまり「相続登記」を行いましょう。これは、亡くなった人の名義を、相続人の名前に変える手続きです。
この相続登記は、2024年4月から義務化されました。相続したことを知った日から3年以内に登記をしないと、10万円以下の過料が科される可能性があります。
「相続したことを知った日」とは、自分が相続人だとわかり、不動産が相続の対象だと知ったときです。その日から3年以内に登記を終えるようにしましょう。
お問い合わせください。
3、共有持分を相続する際の注意点や相続税
共有持分の相続は、思わぬトラブルにつながることがあります。ここでは、よくある注意点や、相続税との関係について説明します。
-
(1)共有持分は権利関係が複雑になるリスクがある
共有持ち分の相続により共有者が増えると、手続きが煩雑になり、不動産の扱いが難しくなるのが大きなリスクです。
たとえば、以下のケースで考えてみましょう。相続財産:家(不動産)
共有者:Aさん(配偶者はおらず、子ども3人)、Bさん
Aさんが亡くなった場合、不動産の共有者はBさんに加えて、Aさんの子ども3人という構成になります。つまり、共有持分を持つ人が4人に増えることになります。
共有者が多くなると、不動産を売る・貸す・建て替えるといった重要な決定をする際、全員の同意が必要になるケースが多くなります。
誰かひとりでも反対したり、連絡がつかなかったりすれば、話し合い自体が進まなくなります。その結果、不動産を活用したくても動かせないという状況に陥るリスクがあります。 -
(2)遺産分割協議がまとまらない場合は遺産分割調停
相続人どうしで話し合いをしても、どうしても意見が合わず、協議が進まないことがあります。共有不動産のように利害がぶつかりやすい財産では、特にこうした事態が起こりやすくなります。
このような場合には、家庭裁判所に遺産分割調停を申し立てることを検討せざるを得ない状況になることもあります。
遺産分割調停では、裁判官と調停委員が第三者として間に入り、中立の立場から話し合いをサポートしてくれます。当事者どうしだけでは解決できなかった問題も、冷静なやりとりの中で整理され、合意に向けた糸口が見えてくることがあります。
それでも話し合いがまとまらない場合は、調停は不成立となり、最終的には「審判」という手続きに移行します。審判では、家庭裁判所が遺産の分け方を判断し、強制的に結論が出されることになります。 -
(3)相続税は不動産全体ではなく共有持分に対してのみ発生する
不動産の共有持分を相続した場合、その相続税は家や土地の「一部」に対してだけかかります。
たとえば、1000万円の土地を2人で半分ずつ持っていて、そのうち1人が亡くなった場合、相続税がかかるのは500万円分の持分だけです。
相続税の計算では、まず土地や建物の評価額を出します。その上で、亡くなった人が持っていた割合(持分)だけを課税対象として計算します。
また、相続税の申告や納付は、亡くなったことを知った日の翌日から10か月以内と決まっているので、早めに行いましょう。
4、共有持分の相続でよくあるトラブルとは│悩んだら弁護士に相談を
共有名義の不動産は、相続後にさまざまな問題を引き起こすことがあります。特に、複数人が関わることで、協議や管理が難しくなり、時間と労力がかかるケースも少なくありません。
ここでは、よくあるトラブルと、それぞれの場面で弁護士に相談するメリットを紹介します。
-
(1)共有者の一部と連絡が取れず、不動産の処分ができない
相続によって不動産の共有者が増えると、その中の一部と連絡が取れなくなるケースがあります。たとえば、住所が不明になっていたり、話し合いを拒否されたりすることもあります。
このような場合、不動産の売却や賃貸などの判断には原則として全員の同意が必要なため、ひとりでも協議に参加しない共有者がいると、手続きが進められなくなってしまいます。
こうした事態に直面したとき、弁護士は状況に応じて、所在調査、通知の送付、家庭裁判所への調停申立てなど、適切な手段を選択してアドバイスします。
また、相手との連絡や交渉も、弁護士が代理人として関与することで、当事者間の緊張を和らげ、よりスムーズに進められる可能性があります。 -
(2)相続人の間で感情的な対立が起き、協議が進まない
共有名義の不動産を相続した相続人どうしで、分け方や今後の扱いについて意見が衝突し、話し合いが進まなくなることがあります。相続にまつわる過去の経緯や感情が絡み、当事者だけでは冷静な協議が難しくなることも珍しくありません。
このような場合、弁護士は中立的な立場から相続人の間に入り、必要に応じて代理人として交渉を代行することができます。感情的な対立を避けながら、論点を整理し、現実的な解決策を探る上で大きな力になります。
さらに、話し合いでまとまらない場合には、家庭裁判所への遺産分割調停の申立ても弁護士が代わりに行うことができます。調停では、弁護士が依頼者の主張を整理し、法的根拠に基づいた交渉を行うことで、円満な合意を目指すことが可能です。 -
(3)共有名義のまま放置し、次の世代に持分が分かれてしまう
共有名義のまま不動産を長年放置してしまうと、次の相続が発生したときにさらに共有者が増え、権利関係が極めて複雑になるリスクがあります。また、関係者が増えることで、意思決定が難しくなり、不動産を自由に活用することができなくなる恐れもあります。
こうした事態を防ぐために、弁護士は、現時点での共有状態を整理し、持分の買い取り、換価分割(売却して代金を分ける方法)、相続登記の整理などを含めた対応方針を提案することができます。
また、相続人どうしで価値の感じ方が異なる場合には、弁護士が不動産鑑定士等と連携し、適正な評価額をもとに公平な協議を進めることも可能です。
このように、弁護士の力を借りることで、時間の経過による複雑化を未然に防ぎ、実現可能な解決へと導くことができます。
5、まとめ
共有名義の不動産は、相続によって持分が複雑化しやすく、適切に対応しなければ、後々のトラブルにつながることもあります。相続人どうしの関係や財産の状況に応じて、早めの判断と手続きが重要です。
少しでも不安な点がある場合は、弁護士のサポートを受けながら進めることで、円満な解決が期待できます。
共有持分の相続でお悩みの方は、ベリーベスト法律事務所 大分オフィスまでお気軽にご相談ください。
- この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています